このうちの庵滝と緑滝の二つの滝のあるのは、前白根山を源頭とし、弓張峠のすぐ先を流れている外山沢(トヤマザワ)である. 幕末から明冶に日本に赴任していたアーネストサトウは、日光を紹介する英文パンフレットの発行に携わるなど、この地に縁が深いのである、明冶十年の旅では白根山で道に迷うという 騒ぎを起こしている.前白根から沢を下っていくと、下降不能な滝の上に出てしまい引き返したことが、彼の日誌に書き残されているのである. そして、「後で知ったのだがこれは外山沢で」とあるから、この沢のどこかの滝の上で引き返したことになる. サトウが遭遇した滝はどこだったのだろう.地形図でも緑沢、庵沢にそれぞれに滝が掲載されているから、百年以上昔の日誌にわずかに出てくる滝を特定することは難しいであろう. 地形図を広げて眺めていると外山沢は勾配も緩そうで、堰堤もないから遡行は容易そうに見えた. その後「奥日光の自然ハンドブック」という本を読んでいると、 庵滝について記載を見つけることができた.高さは20メートル、落差に関しては今ひとつとのようだったが、岩にはさまれ南画の世界であると紹介されていて、景観に期待が高まる. この滝までなら、日帰りで出かけけて行くのにちょうど良さそうに思えた. しかし、日光は少し遠いから、早起きしてまで出かける気になれず、惜しくてたまらない夏の休日が過ぎ去っていったのであるが やはり暑い休日は沢に行きたい. 思い切って昨年から考えていた外山沢のプランを、実行することにした. まずは東京駅に向かう.出発がすでに遅かったから、新幹線で時間を挽回することにした.せっかく特急代を払ったのだが、いつものことながら日光線の連絡が悪く、 日光駅ですでに9時を過ぎてしまった.今日は、まだここから先が長い. 湯元行きバスに乗れば、車窓に繰り返される風景はすっかりなれてしまったものである.夏休みであるだけに、東照宮前は渋滞ぎみだった.いろは坂を登って中禅寺湖北岸、竜頭の滝の上に出て、次は赤沼.ここで低公害バスの乗り 場に急ぐ.ちょうどバスは出発するところであった、どうにか間に合った.もしここから歩いていかなけらばならないとなると一時間ほど必要になるから間に合ってよかった. 国道から閉鎖された市道にバスは入っていく.小田代ヶ原で乗客の多くは降りていった.ここで、降りるべきだったのだが、ひとつ先まで乗ることにした. なかなか出発しないのは、戻ってくるバスを待つからであった.ここの道路はすれ違いできないことを忘れていた. 弓張峠を越え、大きくカーブして下り、外山沢の脇に出る.去年ここで熊を見たことを思い出す.こんな夏の昼間中ならと思うが、大丈夫という根拠はない. 油断はできない、鈴をもってくるべきだったことに気づく. 西ノ湖入口バス停で降りそのまま林道を小走りに進んだ.弓張峠に向かう散策道に入り外山沢に急ぐ.出会う人も少なく快適だ.平坦な歩道はツメタ沢の橋を渡って、 その先の林道を越えたところから山裾を辿るアップダウンの続く道に変わった. そして、前回は雪中で見た、外山沢にかかる木橋の上に出た.時計を見れば、バスを降りてから、結局1時間ほどかかっている.少し時間をロスしてしまったようだ. 水にぬれなくても、いけそうにも感じたのだが、橋の上で一応渓流用のシューズに履きかえて沢に降りた. ぬれないようにルートを探しているよりは、思い切って水に入るほうが登る速度はずっと速くなるはずだ. それに、このあたりは標高は1400メートルもある高地とはいえ、水にぬれて進みたいと感じるほど今日は蒸し暑い. 遡りはじめるとまもなく、水量が急激に減りはじめた.さらに上流に滝があるとは信じがたいほど小さな沢になってしまった. 日陰の部分に足を踏み入れると、厚い絨毯のように敷き詰められた沢底の苔が、踏みつけた一歩を跳ねもどす. 予想にまったく反した光景だった.これでは滝があったとしても涸れ滝ではないかと心配にならざるをえない. どう考えてみても誤った沢を遡行しているはずもなく、ここが外山沢であるから、そのまま進む. 滝訪問は、たまにははずれたりすることもあるのだから、面白さがあるのだと自分に言い聞かせるようになった. ところが、木々の下を抜けると沢幅は広くなり石の河原に戻っていた.まだ水は消えているが、それはここが伏流になっているからだろう. 期待どおり、再び水が現れる.それも、先ほどまでの様子が同じ沢であるとは信じられないほど水量は豊かだ.もっぱら水中で足を進めることにした. 二俣に出る.ここが緑沢と庵沢の合流点と確認する.地形図によれば、どちらの沢に登っても滝があるのである.いずれも見てみたいが、まずは南画のような庵滝を見たいから左俣に入ることにした. 沢底の傾斜は幾分急にはなったが登りはじめるとすぐにも、前方の樹間に一直線に落下する白い垂線が見えてきて胸は高鳴る. 疲れも忘れて駆け上っていくと、前方は壁になっていく手を阻まれ、その岩壁の真中に水は一直線に落下していた. 滝の前に立ち地図を広げてみたけれど、今どこにいるのかわからないように思えた.目の前に落下している滝が、庵滝ならば、地形図によれば、二俣からはかなり奥にいなければならないことになる. しかし実際にはそこからいくらも登ってきてはいない.緑滝なら分岐からさほど奥ではないから、もしかしたら庵沢の出合いを見落とし緑沢まできてしまったのであろうか.でも南画とまでは行かなくて、本に書かれていて思い浮 かべていた姿に滝は似てはいたから、これが庵滝であるようにも思えた.結局、この疑問は解けないまま帰路を急ぐことになった.下りながら確認しても庵沢と思われるような大きな枝沢が合流している気配はない. よって私の入ったのは庵沢であったことになる. しかし、このなぞは四日後に解けた.帰宅し「奥日光の自然ハンドブック」を開いてみると、「日光四十八滝」という本が少し前に出版されていることが記載されている.私家版のようで入手は 難しそうだから、図書館ででも探さなければとは思いながらも、一応オンライン書店で検索してみると、同著者の「日光四十八滝を歩く」という本が、この春出版していることを知った.このところ書店をゆっくりみる こともなかったからうっかり見落としていたようだ.何か手がかりが得られることは確実に思えたから早速注文した. 待ち遠しかった本が届き、開けてみれば、私の訪れた滝はどうやら庵滝であると考えて良いようである.少しややこしいが地形図の庵滝の場所には別の大きな滝があって、いつしか国土地理院ではこの滝 に庵滝という名をつけていたようである.古老の話などから入口の滝のほうが庵滝と呼ぶにふさわしいというのが、この著者の考えだ. 思い起こしてみれば、私は地形図に出てくるこの種のミスをこれまでにも経験しているのであるのだが、自分が山中のときには地形図は疑わないものになってしまっているようだ.人の入ることも少ない山奥に あるのだから、測量の結果と地元に伝わってきた名称を付き合わせていく作業には限界もあるのも無理もない気もする. 滝は自然に存在するが、それを何と呼ぶのかはそれに携わった人次第であるのだからやむ終えない.そして、冷静に考えてみれば、その名前がわずらわしさを与えていたに過ぎない. |
||
| 2000年8月訪問 | ||
| 先日、この沢を遡行した弘田さんから、地形図に載っている方の滝の写真をいただきました. 2001年6月. |
|
 |
 |
||||
| 水流の細くなってしまった沢. | 川幅は再び広くなったが、水は流れていない. | |||||
| <参考文献> アーネストサトウ 著 庄田元男訳 日本旅行日記 2 東洋文庫550 平凡社 1992年 // 宮地信良 編 奥日光自然ハンドブック 自由国民社 1997年 // 奥村隆志 著 日光四十八滝を歩く 随思社 2000年 | ||||||
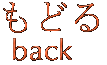 |
 |
 |
Copyright(C)2000-2009 Masashi Koizumi.All Rights Reserved.
